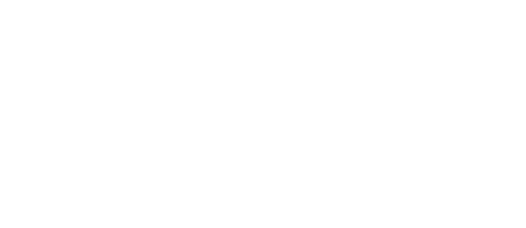海外志向が低迷する日本人:パスポート保有率の減少が示す内向き傾向
2024年に発行されたパスポートは382万冊と報じられました。前年と比べて30万冊増加したものの、新型コロナウイルス感染拡大以前の2019年と比べると約70万冊の減少です。日本人のパスポート保有率は「6人に1人」の計算ともいわれ、5人に1人を下回る水準に落ちこんでいます。円安による渡航費用の高騰や若年層の海外志向の変化など、複合的な要因が背景にあると考えられます。
かつては「世界の何でも見てやろう」というフレーズが象徴するように、海外に積極的に出る日本人が多い時代もありました。とりわけ1980年代は海外旅行がブームとなり、「憧れのハワイ航路」に象徴されるような海外渡航者数の増加が続いていました。しかし現在では、訪日外国人が増加する一方で、日本人出国者数は大きく減少しています。グラフ上でも訪日外国人が右肩上がりに伸びていく一方、日本人の海外渡航数は低迷を続け、コロナ禍を経た今も回復しきれていません。
こうした状況は「イオニスト」という言葉にも集約されているといわれます。イオンモールを行動範囲の中心とし、高校時代の友人と毎週のように集合し、結婚式や子育て、さらには葬式までイオンモールで完結させてしまう——そのように20キロ圏内で大半の用事を済ませる人々を指す揶揄的な表現です。もちろん全員が同じわけではありませんが、海外どころか国内すら積極的に見て回る発想に乏しい人が増えていることを示唆しています。
このような傾向は、高齢世代にも表れています。長引くコロナ禍で、海外旅行に行く機会や意欲を失い、高齢になってからは「ヨーロッパ旅行なんて体力がもたない」と断念する人が増加しました。結果的に使い道が限られる貯蓄が積み上がり、国内の高級飲食店など、一部の業界にお金が集中する現象も生まれています。特に寿司店がバブルとも呼ばれるほどの価格帯で新規出店や予約待ちが発生する一方、他の外食ジャンルや地方への旅行などはそれほど伸びていないという指摘もあります。
こうした国内回帰志向は、若者の海外留学や海外赴任への志願者減少とも関連しているでしょう。グローバルな視野をもたなければならない時代に、海外に出る人が減り続ける現状は、企業の国際競争力や日本社会の活力にも影響を及ぼしかねません。
国内経済の現状:名目GDPは最高値だが、実質成長は伸び悩み
内閣府が先月公表した2024年の名目GDPは609兆2887億円となり、前年比2.9%増で過去最高を記録しました。半導体関連を中心とした設備投資の活発化や物価上昇が押し上げ要因とされています。しかし、物価変動の影響を除いた実質GDPは557兆円程度にとどまり、前年比0.1%増とほとんど伸びが見られません。
名目ベースでは増加しても、実質ベースではいまだに低成長という日本の状況は長らく続いています。公共事業の伸びが限定的である一方、家計消費と民間設備投資は顕著に上向きつつあるものの、物価高による購買力低下や先行き不透明感が重石になっていると考えられます。実際、コロナ禍で貯蓄が積み上がった高齢世代は「近場で気軽に楽しむ」選択肢をとりやすく、旅行や外食が「遠出」よりも「地元での消費」に向いている傾向も見られます。
このように、名目GDPの数字だけでは日本経済の「底力」を測るのは難しい時代になっています。生産性の向上やイノベーションへの投資、人材育成など、成長のエンジンとなる領域での改革が求められるといえるでしょう。
日立製作所に見る企業改革の成功例:“ラマーダ戦略”と選択と集中がもたらす高時価総額
日立製作所の株価が先月、終値で初めて時価総額20兆円を超えました。その背景には、長年進めてきた大規模な事業構造改革があります。かつては家電や鉄道、電力など多岐にわたるハード中心の製品群を扱っていましたが、近年はITサービス・インフラ分野を中心に“選択と集中”を徹底。いわゆる「ラマーダ戦略」と呼ばれる手法で、収益性の低い事業は大胆に切り離し、利益率の高い分野に経営資源を投下してきました。
この戦略は投資家から高く評価され、電機メーカー各社の中でも特に日立とソニーが頭一つ抜けた時価総額を誇るようになりました。ソニーが映画・音楽・ゲームといったエンターテインメント分野で好調を維持する一方、日立はITやインフラを組み合わせたソリューションを強みとしています。逆にパナソニックや富士通は売上規模の割に時価総額が伸び悩んでおり、改革のメリハリが株式市場から見えてこない点が課題といえるかもしれません。
大企業だからこそ、複数の事業を抱えて全方位に手を広げがちです。しかし、変化の早い時代には、明確な勝ち筋を見極めて素早く舵を切るかどうかが企業価値を左右します。日立の事例は、今後の日本企業全体にとっても示唆に富む成功例といえるでしょう。
富士ソフトをめぐるTOB攻防:アメリカ勢ファンドの争奪戦に見る経営陣と創業家の思惑
システム開発大手の富士ソフトをめぐるTOB(株式公開買付)は、米国ベインキャピタルと米国KKRという2大ファンドの争奪戦として注目を集めました。最終的にはKKRが買い付け価格を1株9850円まで引き上げたことを受け、ベインキャピタルが撤退。KKRによる買収が成立する見通しとなりました。
富士ソフトの創業家である野澤氏はすでに経営の第一線を退いており、一方で現経営陣はKKRによる買収案を支持していたとみられています。株価は買付価格をめぐる報道のたびに大きく跳ね上がり、最終的にKKR陣営が提示した高値で落ち着くことになりました。
富士ソフトはシステム開発以外に不動産でも実績を上げてきた企業で、駅周辺の好立地物件を多く保有していることが特徴です。ただし、その不動産価値を含めても、時価総額全体の割合からすると極端に大きいわけではなく、同社買収の真の狙いはIT関連事業の成長性にあるとも言われています。
創業家にとっては大きな資金流入が期待できる一方、ファンドにとっても企業価値向上の余地があると判断したのでしょう。今回の争奪戦は、日本企業の所有構造やファンドの役割が変化している一端を示すケーススタディとなりました。
アステラス製薬の成長戦略:バイオベンチャー投資で特許切れリスクに挑む
製薬業界では、特許切れのタイミングが企業の将来を左右する大きなリスクとして常に注目されています。アステラス製薬の場合、前立腺がん治療薬「エンザルタミド(商品名イクスタンジ)」の特許が2027年前後から切れる可能性があり、同社の売上構成においてこの製品が大きな割合を占めるため、いわゆる“パテントクリフ”の懸念が存在します。
こうした危機感を背景に、アステラスは海外バイオベンチャーへの積極投資やM&Aを進めてきました。最近ではイギリスのフォアモースト社への出資を発表し、がん細胞のタンパク質を分解する技術を獲得することで、自社にない技術を補完しています。新薬開発では、多額の投資を要する一方で失敗リスクも高く、投資家目線では株価が過小評価される傾向に陥りがちです。
一方、大塚製薬や中外製薬のように、特許切れリスクを超えるブロックバスター製品を生み出すことで時価総額を拡大してきた例もあります。アステラスが同じ軌道に乗るには、有望なパイプラインの育成と成功確率の高い開発が必要です。M&Aや投資先との連携を通じてどこまで特許切れの落差を埋められるかが、今後の株価や企業価値を左右するでしょう。
—この記事は2025年3月2日にBBTchで放映された大前研一ライブの内容を一部抜粋し編集しています。