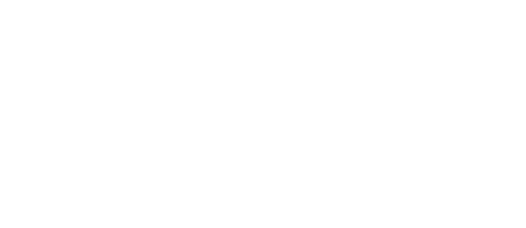▼日産の新体制と自動車業界の再編動向
経験を重視した戦略的人事
日産自動車は11日、新しい役員体制を発表しました。この発表の中で注目されるのは、スティーブン・マー氏がCFO(最高財務責任者)の職を離れ、中国事業の統括責任者に就任する一方で、新CFOには北米日産社長として活躍してきたジェレミー・パパン氏が任命されたことです。これについて、内田誠社長兼CEOは、「会社を再び軌道に戻すため、経験と緊急性を考慮した人事である」と説明しました。
この人事は、近年の同社の課題である世界市場での競争力回復や収益性向上に向けたものと見られています。特に中国事業は、日産にとって成長の鍵を握る重要な市場であり、スティーブン・マー氏がその手腕を発揮することが期待されています。また、北米での実績を持つジェレミー・パパン氏の財務戦略が、日産の全体的な経営改革を支えることが見込まれます。
メキシコでの生産体制も、日産の競争力に大きく寄与してきた要素の一つです。古くからメキシコで車両を生産し、アメリカ市場へ輸出する仕組みは、現在も続いていますが、トランプ前政権の政策により25%の関税が課される可能性があると指摘されています。これにより、メキシコ工場の存続が問われる状況にあり、同社にとって極めて重要な課題となっています。
さらに注目すべきは、こうした日産の動きが、グローバル自動車市場で進行中の再編の一環として位置づけられる点です。特にアメリカや中国市場での競争が激化する中、日産の動向は他の自動車メーカーにとっても重要な参考例となるでしょう。
▼ホンダ・日産の経営統合に見る日本の自動車業界の変革
一方で、ホンダと日産が経営統合に向けた協議を開始したというニュースが、自動車業界全体を揺るがしています。この協議には、三菱自動車の合流も検討されており、最終的には世界第3位の自動車グループを形成することを目指しています。
経営統合の背景には、両社が抱える課題が存在します。特にアメリカや中国市場での販売台数減少や工場閉鎖、人員削減といった問題が深刻化しており、これに対処するために経営資源を結集する必要性が高まっています。また、三菱自動車が持つアジア市場での強みや、オーストラリアやニュージーランドでの高いブランド力を活かし、グローバル市場での競争力を強化する狙いがあります。
しかし、こうした統合が実現するには課題も多くあります。ホンダと日産はこれまでにも独自の経営スタイルを貫いてきたため、企業文化の違いや統合後の運営戦略が大きなハードルとなる可能性があります。特にホンダは二輪車事業での収益が高く、乗用車分野では日産と異なる市場アプローチを取っているため、統合後の方向性が一致するかどうかが鍵となります。
また、統合によって生じるスケールメリットを活かせるかどうかも重要な論点です。特に統合が進むことで、販売台数は800万台に達し、グローバルトップ3に位置する可能性がありますが、一方でそれに伴う運営コストや調整コストが利益を圧迫するリスクも考えられます。
さらに、他の大手メーカーの状況にも注目が必要です。フォルクスワーゲンやGMなど、多くの大規模自動車メーカーが現在苦境に立たされており、中国市場での成功に依存していた点が裏目に出ている状況です。これらの状況を踏まえると、日本のメーカーがいかにして持続的な競争力を維持するかが問われています。
▼グローバル自動車市場におけるSDVの進化と日本メーカーの挑戦
ソフトウェアが定義する車(SDV)の未来
世界的に自動車の開発トレンドが大きく変化しています。その中心にあるのが”Software Defined Vehicle (SDV)”、すなわちソフトウェアで機能を追加・更新できる車両の開発です。この分野では、すでにテスラや中国のBYDといった企業が先行しており、開発費用も莫大なものになっています。
日本の自動車メーカーは、これまで系列企業を通じた強固なサプライチェーンを構築してきましたが、SDVの普及によりその優位性が揺らいでいます。特に、中国のシャオミやファーウェイ、アメリカのテスラが進める異業種連携に対し、日本勢は対応の遅れが目立っています。
さらに、自動運転技術の進展もSDVの重要な要素となっています。この技術の進化には、膨大な走行データと高精度な解析が必要ですが、日本ではこれを十分に確保できていない状況です。アメリカやシンガポール、中国などの一部地域が自動運転データ収集で先行している中、日本のメーカーはデータプラットフォームの整備を急務としています。
この分野では、異業種からの参入も増加しており、アップルやホンハイ(フォックスコン)の動向が注目されています。特にホンハイがアップルと連携して開発を進めるEV(電気自動車)は、次世代のモビリティ市場で競争力を持つ可能性が高いとされています。これに対抗するため、日本のメーカーもさらなる技術革新と提携戦略を進める必要があります。
▼西武ホールディングスとブラックストーンの資産売却戦略
西武ホールディングスは、東京ガーデンテラス紀尾井町をアメリカの投資ファンドであるブラックストーンに約4000億円で売却すると発表しました。この施設は、赤坂プリンスホテルの跡地に開発された複合施設で、西武にとっては資産売却を通じて負債返済と主要ホテルの価値向上を図る重要な一手です。
一方で、ブラックストーンがこの施設をどのように活用するのかについては不透明な部分もあります。同社はテナント誘致においてこれまで大きな実績を残しているわけではなく、今後の運営計画が注目されています。
▼日韓航路からの撤退:JR九州の苦境
JR九州は、博多港と韓国釜山港を結ぶ高速船”クイーンビートル”の運行再開を断念しました。この背景には、浸水事故や虚偽報告による行政処分が重くのしかかっています。この航路は、日韓間の観光需要や地域交流を支える重要な役割を果たしていただけに、再開断念の決定は大きな衝撃を与えています。
特に、福岡と釜山を結ぶこの航路は2時間55分という短時間で結ばれており、自転車旅行を楽しむ観光客にも人気のルートでした。コロナ禍による往来減少が追い打ちをかけた形となり、地元経済への影響も懸念されています。
▼エンターテインメントの新展開と地域経済への影響
ユニバーサルスタジオジャパンの挑戦:ドンキーコングカントリー
ユニバーサルスタジオジャパン(USJ)は、新エリア”ドンキーコングカントリー”を開業しました。このエリアでは、任天堂の人気ゲーム”ドンキーコング”をテーマにしたトロッコ型ジェットコースターなどが楽しめます。このプロジェクトは、来年アメリカ・フロリダ州でも開業予定のユニバーサルエピックユニバースに続くものであり、日本発のエンターテインメントコンテンツのグローバル展開を象徴しています。
USJは、ディズニーランドとディズニーシーから成る東京ディズニーリゾートに次ぐ入場者数を誇るテーマパークとして成長を続けています。その背景には、大阪という立地を活かした地域密着型の戦略がある一方で、世界規模での展開を見据えた長期計画が存在します。
また、この新エリアの開業は、テーマパーク業界全体の競争力向上にも寄与しています。特に大阪府が進める万博計画との相乗効果を期待する声もある一方で、資金配分や運営戦略の課題も指摘されています。
—この記事は2024年12月22日にBBTchで放映された大前研一ライブの内容を一部抜粋し編集しています。