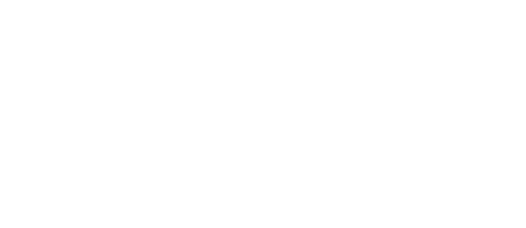Aoba-BBTとアルムナイが生み出す“学びの生態系” 学ぶ・集う・創る──コミュニティの力が価値を再生産する
私が創業したAoba-BBTでは、学習プログラムを提供して終わり、という発想はしていません。在校生と卒業生が互いに刺激し合い、新たな価値を生み出す「学びの生態系」をつくることを重視しています。アルムナイを巻き込んだセミナーや、アルムナイコミュニティ”LEN (Lifetime Empowerment Network)”による地域イベントは、その象徴的な取り組みです。
とくに構想力イノベーション講座では、築地・勝どき・晴海・豊洲といった湾岸エリアを題材に、受講生が自ら都市構想を描き、議論し合うプロセスを重視しています。単なる“講義を受ける場”ではなく、都市や産業の未来を自分の頭でデザインしてみる。その経験そのものが、学びの価値を大きく引き上げると私は考えています。
”LEN (Lifetime Empowerment Network)”の活動もユニークです。中野区で活躍する卒業生を囲んだ小規模イベントでは、地域産業のリアルに触れ、ローカルコミュニティとの接点を広げる機会が生まれました。学びの場がキャンパスの中に閉じないこと、卒業後も“学び続ける動機”をコミュニティが支え続けることは、現代の教育機関が担うべき重要な役割だと見ています。
こうした取り組みは、私たちAoba-BBTが掲げる「生涯学び続けるプラットフォーム」という理念にも合致しています。オンラインの強みを生かしつつ、リアルなフィールドワークや卒業生同士の交流が自然に連動することで、学習成果は個人の成長だけでなく、社会への価値還元にもつながっていきます。
教育は、“資格取得”や“単位消化”の場では終わりません。“未来をつくる力を共に育む場”へと進化させていくことこそ、私がAoba-BBTで追求している方向性です。
移民受け入れの鍵は「慣れ」である―義務教育の“1年間海外生活”という大胆な発想
日本社会が移民受け入れに慎重な最大の理由は何かと問われれば、私は「慣れの欠如」だと答えます。治安や文化摩擦、雇用競合といったリスクを議論する以前に、多くの日本人は、そもそも外国人と一緒に生活した経験がほとんどありません。この“経験の空白”こそが、構造的な問題だと私は見ています。
その解決策として、私は「義務教育12年のうち、1年間を海外で生活する制度」を提案しています。義務教育1人あたりの年間補助額は約60万円です。この水準であれば、東南アジアの比較的安全な国では、生活費を含めても十分に暮らせます。つまり、発想を転換すれば、決して夢物語ではなく、現実的な制度設計が可能なのです。
若い頃から異文化に触れ、異なる価値観や言語に自然に適応する経験を積めば、移民や外国人と共に暮らすことに対する心理的ハードルは確実に下がります。すでに群馬県太田市や、熊本県TSMC関連地域では、外国人労働者が地域経済を支えていますが、住民側も次第に“共に暮らす”ことに慣れつつあります。これは社会が多様性を自然に受け入れていく典型的なプロセスです。
私が提案しているのは、単なる移民政策ではありません。人口減少と労働力不足に直面する日本が、社会の受容力そのものを高めるための教育改革です。国としての「免疫力」や「対話能力」を鍛えるために、若い世代に海外生活の経験を組み込む。これは、日本の未来を見据えた「文化的インフラ」としての教育投資だと考えています。
移民を「外から来る脅威」と見るのか、「共に社会を支える仲間」と見るのか。その分岐点は、制度よりもまず、私たち一人ひとりの経験と慣れにあります。だからこそ、私は教育の中に“1年の海外生活”を組み込むべきだと主張しているのです。
日本の大学はなぜ世界で埋没していくのか―教授システムが「20年遅れ」を構造的に再生産する
QSアジア大学ランキングで日本の順位低下が続く中、文部科学省は学部再編や国際連携強化を掲げた大学改革実行プランを打ち出しています。しかし私は、現在の大学教員制度を前提とする限り、この改革は「実現がほぼ不可能」だと見ています。理由は明快で、日本の教授昇進システムが“時代から20年遅れた人材”を構造的に生み出してしまう設計になっているからです。
大学卒業後、修士・博士課程を経て、助手・助教・准教授・教授へと進むアカデミックキャリアは、一見すると安定した制度に見えます。しかし実態としては、指導教授の研究領域や価値観を継承する形で人事が回っており、世界の最先端の研究潮流や産業界の変化と十分に接続されていません。結果として、大学は「世界最先端を切り拓く場」というより、「学内ロジックと既得権を守る場」になりつつあります。
私がよく例に挙げるのはMITやケンブリッジ大学です。彼らは、世界中から最高水準の研究者をスカウトし、競争力の低い教員については容赦なく入れ替えます。大学という組織そのものが常に揺さぶられ、新しい分野が生まれ、古い分野が整理されていく。この“新陳代謝”が、大学の競争力の源泉です。
一方、日本の大学では、教授職は実質ライフタイムで、内部昇格が一般的です。国際的な人材流動は極めて限定的で、外部からの強烈な刺激が入りにくい構造になっています。その結果、世界ランキングが低下するのは当然の帰結だと私は考えています。
教育は国家の未来を左右する最重要インフラです。だからこそ、日本の大学は「国際競争の中で選ばれる大学とは何か」という根本的な問いに真正面から向き合わなければなりません。改革の本丸は、学部再編や看板学部づくりではなく、教授人事と組織の新陳代謝をどう設計し直すかにあります。そこに手をつけない限り、日本の大学が世界で埋没していく流れは止まらないと、私は強く危機感を持っています。
AIと電力制約を巡る誤解—「日本にデータセンターを作らなければ乗り遅れる」という思い込みを正す
生成AIの進化に伴い、世界中でデータセンター投資が加速しています。その一方で、日本では「電力供給が不十分だからAI産業が育たない」「日本にも大規模データセンターをつくらないと乗り遅れる」といった議論が目立つようになってきました。私は、この議論は本質を外した“誤解”だと考えています。
AIの付加価値は、“データセンターがどこにあるか”ではなく、“AIをどう使いこなすか”にあります。巨大なモデルの学習も推論も、今やグローバルなクラウドインフラ上で行われます。ユーザーが日本にいようが、物理的なサーバーが北欧やアメリカにあろうが、高速な通信回線さえあれば実務上の差はほとんどありません。
それにもかかわらず、日本では「自前のデータセンター」を持つこと自体が目的化しているように見えます。私は、この発想に強い違和感を覚えます。日本はAIモデル開発の技術的中核を握っているわけではなく、箱だけ作っても“中身がないデータセンター”になるリスクが高いからです。電力コストや自然条件で優位な地域にセンターが集約されていくのは、世界的な合理的トレンドです。
本来、日本が注力すべきは、AIを産業・行政・教育にどう統合し、生産性と付加価値を最大化するかという「AI活用戦略」です。データセンター建設を国家プロジェクトの中心に据えるのではなく、「世界最強のインフラがすでに外にある」という前提で、それをどう賢く使い倒すかを設計すべきなのです。
AI時代において本当に求められるのは、物理的資産ではなく、技術を自国の価値創造につなげる知恵とスピードです。思い込みを捨て、発想を根本から転換できるかどうかが、日本の競争力の試金石になると、私は見ています。
台湾・中国・高市発言問題が示す日本外交の脆弱性—曖昧戦略すら扱えない政治の危うさ
高市首相による「台湾侵攻が武力を伴うものであれば存立危機事態になり得る」という発言は、中国側の強烈な反発を招きました。中国の総領事による過激な投稿も加わり、事態は予想以上の緊張をはらむものになっています。私は、この問題の本質は「発言そのものの是非」よりも、「外交リスクを踏まえた戦略的判断が欠如していること」にあると考えています。
中国は台湾を「完全な内政問題」と見なしています。そのため、他国が軍事介入を想起させる発言をすると、国内世論が一気に高ぶりやすくなります。過去にも反日デモや日本人への嫌がらせが繰り返されてきましたが、そうしたリスクを十分に織り込んだうえで発言しているようには見えません。
私が重要だと考えているのは、対中関係の激化を避けつつ、日本の立場と安全を守るための「複数の裏ルート」をどう活用するかです。たとえば、茂木外相が静かに中国側と話をつけるルート、トランプ経由で習近平に水面下のメッセージを送るルート、公明党を通じて空気を和らげるルートなど、カードはいくつかあります。本来、外交とはそうした多層的なチャンネルを使い分ける“職人芸”の世界です。
さらに、日本が最も警戒すべきは「台湾有事=日本有事」という構造です。中国と米国が台湾を巡って衝突し、在日米軍基地が攻撃されれば、日本は自動的に戦争に巻き込まれます。だからこそ日本は、中国に対して「台湾有事の際にも在日米軍基地を攻撃しない」という明確な保証を引き出すべきだと私は考えています。
今回の一連の動きは、日本外交の未熟さと準備不足を浮き彫りにしました。米国が採っている“曖昧戦略”の意味も理解せず、国内向けの強硬発言で自己満足しているだけでは、国益は守れません。いま日本に最も欠けているのは、感情ではなく戦略で動く冷静な外交力だと、私は強く感じています。
企業ニュースが映し出す「勝者」と「迷走者」—資生堂、USスチール、独自動車3社、サイバーエージェントの明暗
番組の後半では多くの企業ニュースを取り上げましたが、私がそこから読み取っている共通テーマは、「経営の質の差が業績にそのまま表れている」という点です。
資生堂の2期連続赤字見通しは、長く続いた成功体験に依存した経営が、一気に裏目に出た典型例だと私は見ています。とくにアメリカでのM&A失敗による巨額損失は、グローバル戦略の目利き不足を露呈しました。USスチールの巨額投資計画についても、私は「やりすぎ」だと指摘しました。政治的圧力や雇用維持の論理に引きずられた投資は、長期的には企業体力を削りかねません。
一方、ドイツの自動車産業では、フォルクスワーゲンやメルセデスがEVシフトと関税の逆風で苦戦する中、BMWは堅調な利益を維持しています。“流行に過剰反応せず、自社の強みであるエンジン車を徹底的に磨き続けた”という戦略が功を奏していると私は評価しています。
サイバーエージェントも興味深いケースです。インターネット広告とゲームで稼ぎつつ、長年「アベマ」という赤字事業に投資を続けてきましたが、ようやく黒字化の目処が見えつつあります。これは、長期戦略の成功モデルの一つです。しかし同時に、創業者が代表権を持った会長として残り続ける構図には、私は批判的です。創業者の影響がいつまでも強く残ると、後継経営陣が本当の意味で自律できないからです。
これらの事例が示しているのは、企業は「環境変化への適応スピード」と「意思決定の質」によって、いかようにも“勝者”にも“迷走者”にもなり得るということです。経営の本質は、目先の流行に乗ることではなく、環境変化の構造を読み解き、自社の強みと結びつける洞察力にあります。そこを見誤った企業から順番に、市場から退場を迫られる時代になっていると、私は感じています。
独裁・汚職・権威主義の不安定化:ロシア・ウクライナ・中東の現在地
ロシア、ウクライナ、シリア、トルコ──番組で取り上げたこれらの国々には、共通した構造があります。それは、「国家の意思決定が制度ではなく個人に依存し、その個人の判断ミスがそのまま国家の危機に直結してしまう」という危うさです。
ロシアでは、ラブロフ外相の行方を巡る憶測が飛び交い、政権の不透明さが一段と深まりました。人民元建て国債の発行は、制裁でドルやユーロが使いにくくなった結果ですが、同時に財政運営が追い詰められていることの裏返しでもあります。
ウクライナでは、国営原子力企業をめぐる汚職疑惑で閣僚2人が辞表を出しました。戦時下にもかかわらず、国防やエネルギー分野でキックバックが横行している現状は、国家の脆弱性を象徴しています。
シリアでは、トランプが“元アルカイダ系指導者”とされる人物をホワイトハウスに招いたというニュースがありました。これは、アサド政権崩壊後のシリアをアメリカ側に取り込もうとする動きですが、手法としては極めて危ういバランスの上に成り立っています。
トルコでは、エルドアン大統領が最大野党のイマモール氏に“禁固2352年”という常識外れの求刑を行い、司法の独立が完全に形骸化していることを世界に示してしまいました。
これら一連のニュースは、権威主義国家が抱える「制度の欠如」という致命的な弱点を浮かび上がらせます。リーダーの恣意的な判断が国家の進路を決め、ブレーキ役となるべき司法や議会は機能不全に陥る。その結果、外から見ていても、意思決定の質がどんどん劣化していく様子が手に取るようにわかります。
民主主義国である日本も、この問題を対岸の火事と見なすべきではありません。制度の強さこそが、最終的には国の安定と国民の安全を守ることを、これらの国々の事例は教えてくれていると私は思います。
75歳以上が“都会へ移住”する時代—高齢者が都市を選ぶのは「便利だから」ではなく「生きやすいから」
日経新聞が「ついの住処 都会に求める」という記事で、75歳以上の高齢者が生まれ育った自治体から他の市区町村へ転出する動きがこの10年で3割増えたと報じました。私は、これは日本社会の構造変化を象徴する重要なサインだと見ています。
従来、「老後は静かな地方で」「生まれ育った土地で人生を終える」という価値観が強くありました。しかし現実には、地方では医療・介護サービスが限られ、買い物や通院の負担も大きくなっています。子ども世帯が都市部に住んでいる場合、親を遠方で支えることは非常に難しく、結果として「親を呼び寄せる」動きが加速しています。
私は、都心で暮らす高齢者が増えている理由を、“文化や娯楽が近いから”という表層的な説明だけでは捉えきれないと考えています。むしろ、高齢者にとって不可欠な「医療へのアクセス」「公共交通」「日常の買い物」「社会的つながり」が徒歩圏で完結する点こそが、都市の本当の価値です。
欧米でも、高齢者が地方の一軒家を手放し、都市のコンパクトな住まいへ移る動きが進んでいます。これは日本特有の現象ではなく、高齢化と都市機能の集中が同時並行で進む先進国共通のトレンドです。
一方で、都市に高齢者が集まることで、医療・介護サービスの逼迫や、住宅価格の上昇による世代間格差など、新たな課題も生まれます。「高齢者にとっての都市のあり方」をどうデザインし直すかは、今後の都市政策の中核テーマになるでしょう。
高齢者が都市を選ぶのは、単に「便利だから」ではなく、「自立した生活と人とのつながりを保ちやすいから」です。その現実を直視し、都市を“高齢者に冷たい場所”から“高齢者が生きやすい場所”へと変えていくことが、日本社会の次の課題だと私は考えています。
—この記事は2025年11月16日にBBTchで放映された大前研一ライブの内容を一部抜粋し編集しています。