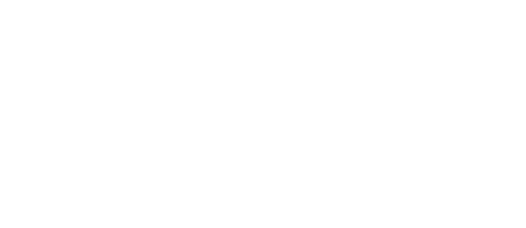小選挙区制度:「二大政党」を生まなかった30年の誤算
小選挙区制度が導入されてから約30年が経過し、当初は「二大政党制に収斂する」と言われたはずの政治構造が、実際にはそうなっていない状況を目の当たりにしています。石破総理も「制度を変えれば二大政党が実現すると考えたのは誤りだった」と認めましたが、今この時点で振り返るのはあまりに遅いと感じます。
私は、小選挙区制度が地域ごとに議席を1名ずつ配分する一方で、“比例代表の救済措置”を組み合わせることで、国全体の大局的な課題に取り組む人材が育ちにくい構造を生んだと考えています。大選挙区や中選挙区であれば、複数の候補者が政策論や国家ビジョンを競い合う土壌が整いやすいものの、小選挙区と比例代表の併用は「小粒な議員」を量産しがちです。
また、現職議員にとっては自らが勝ち抜いてきた選挙制度を変えることは不利になるため、抜本的な改革が極めて難しいのも事実です。私がもし“一日独裁者”になれるなら、真っ先に選挙制度を見直します。それほどまでに小選挙区制度は日本の政治を窮屈にしていると感じていますが、実際には現行の政党政治の枠内で制度を変えるハードルは高いでしょう。今こそ、有権者の意思をもっと正しく反映できる選挙制度を再構築する必要があると思います。
2025年度予算案と高額療養費制度:修正協議の舞台裏と政策判断の遅れ―
2025年度予算案と税制改正関連法案が、高校授業料の無償化などを巡る修正協議を経て衆議院を通過しました。石破総理は「試行錯誤があった」と語り、高額療養費制度の方針転換では「検討プロセスの丁寧さを欠いた」と述べていますが、この一連の流れを見ていて、拙速な意思決定のリスクを改めて感じます。
今回、政府は医療費の自己負担上限を引き上げる考えを示していましたが、患者団体や野党、そして世論の反発を受け、結局撤回に追い込まれました。高額療養費の財政影響自体は数十億円規模とされ、社会保障全体から見れば決して巨大ではありません。それでも「わずかでも負担増」の印象は非常に強いため、国民の理解を得ないまま進めようとすると大きな批判を浴びるのは当然といえます。
私は、このような社会保障政策にこそ、丁寧な情報開示とシミュレーションを通じた合意形成が欠かせないと思います。拙速に進めれば後退・撤回を繰り返し、結局は国民の不信感だけが残るからです。政権への信頼を保ち、財政と国民負担のバランスを再検討するためにも、十分な説明責任を果たす姿勢が重要です。
医療用医薬品と国民医療費の課題:市販薬との価格差と膨張し続ける医療費
医療機関で処方される解熱鎮痛薬や湿布薬などが、市販薬と比べて大幅に安価(1/10以下)で提供されているとの調査結果が出ました。患者にとっては負担が軽いように見えますが、これが過剰な受診を促し、医療保険財政に重くのしかかっている構図があると私は考えています。
同じ成分の薬なら、わざわざ病院に行かずに薬局で購入するほうが財政的には合理的です。しかし日本の医療制度では、医師の処方箋による薬価適用が優遇されるケースが多く、患者の自己負担が少額に収まるため「ちょっとした風邪でも病院に行く」行動が根づいています。その積み重ねが国民医療費の膨張を招き、医療サービスの持続可能性を脅かす要因になっていると思います。
私は、財政負担を軽減するためにも「市販薬で十分対応できる疾患は保険の対象外にする」など、段階的に制度を見直すべきだと考えます。薬局調剤費や調剤報酬といった仕組みも含め、国民皆保険制度を守り抜くにはメリハリのある適正化が欠かせません。
日本郵政とゆうちょ銀行の株式売却:「経営の自由度向上」の真意はどこにあるか―
日本郵政がゆうちょ銀行の株式を追加売却し、議決権比率を約49.9%に下げると発表しました。理由としては「経営の自由度を高める」ことが挙げられていますが、私は「実質的には日本郵政が資金を確保したいのではないか」という見方もあると考えています。
実際、郵便事業はネット時代に入って収益環境が悪化しており、一方でゆうちょ銀行は全国規模のネットワークと莫大な預金残高を武器に比較的安定してきました。今回の売却によって第三者の株主が増える可能性も高まり、国内外の金融機関が“買収”を狙うケースが出てくるでしょう。
ただし、高値で売れた場合に得られる巨額資金を郵便事業の赤字補填に回してしまうと、国民が享受できるメリットが十分に見えなくなる恐れがあります。私は「株式売却後にゆうちょ銀行がどう経営戦略を描き、日本郵政グループとどう関係を保つのか」を注視すべきだと思っています。単に日本郵政が資金を作って終わり、というだけでは国民負担の軽減にもサービス向上にもつながらないでしょう。
NTT法改正論議の行方:固定電話の全国一律提供義務と競争自由度―
総務省はNTT法と関連法案の改正案を示し、固定電話を全国一律で提供する義務を一部緩和する一方、政府のNTT株保有義務などは当面維持する方向を打ち出しました。NTT法の全面廃止は、施行後3年をめどに改廃を検討するとされ、いわゆる“先送り”状態です。
私は、NTTが元々国営の独占事業体だったことから、ユニバーサルサービス(全国一律の通信インフラ提供)を継承しつつ、事業の自由度が他社より狭いという状況が問題だと考えています。一方でKDDIやソフトバンクなどは、網羅的なサービス義務を負わずに自由にビジネスを展開してきました。NTTを縛ったままにしておいたほうが自社に有利という競合他社の意向と、NTT自身が国際競争力を高めるために身軽になりたい思惑がぶつかる構図があるのです。
世界規模で見れば、NTTはもはや極端な巨大企業ではありません。私は、日本の通信市場を活性化し、国際競争力を強化するには、NTT法の廃止や抜本改正を視野に入れた公平なルールづくりが必要だと思います。ただし、その過程でユニバーサルサービスをどう維持するかという問題は避けて通れず、政治的な調整力が求められるのも確かです。
「高コスパ車種ランキング」に見る日本車の強み:アメリカ市場で1位から8位まで独占―
アメリカの中古車情報会社の調査によると、年間あたりの実質コストが最も安い車種ランキングで、日本車が1~8位を独占したと報じられました。ホンダ・シビックやトヨタ・カローラなど、大衆向けモデルの耐用年数とリセールバリューの高さが評価された結果です。
私は、こうした調査結果こそ日本メーカーが積極的にアピールすべきだと思います。EVや先端技術に注目が集まりがちですが、従来のガソリン車やハイブリッド車でも、品質や耐久性を徹底的に高めてきた“ものづくり”の底力があるからこそ、「コストパフォーマンス最強」の座を確立できているのです。
一方、日本国内ではカローラを年収比で見ると5割程度に上昇し、国民車とは言いづらくなっているとの報道もあります。これは長引く賃金停滞を反映しており、単に車の性能だけでなく、日本の経済構造の課題を浮き彫りにしているとも言えます。高品質な車を手頃な価格で提供し続けるには、国内所得の底上げも必要だと感じています。
日本版ライドシェアへの布石:タクシー買収で参入する「ニューモ」の戦略
「ニューモ」が中小タクシー会社を買収し、日本版ライドシェアの実現を目指していると話題になっています。現行法では旅客運送は二種免許が必要なため、アメリカのUberのような形式は広がりにくいのが現状です。そこでニューモは、既存のタクシー会社を一括して傘下に収めることで、ライドシェアに近いモデルを構築しようとしているわけです。
私は「GO」を展開する日本交通グループや、海外大手のUberが日本市場へ本格的に参入してくる動きを見ても、ライドシェアを巡る競争は一段と活発化すると考えています。規制が緩和されれば、個人の自家用車を活用するサービス形態も一気に普及する可能性があり、新興企業や既存タクシー会社、外資系企業がそれぞれの戦略をぶつけ合うでしょう。
同時に、地方や観光地などでの交通確保など、タクシー業界が果たしてきた社会インフラ的な役割をどう維持するかという課題も残ります。私は、こうした公共性とビジネス効率の折り合いをどうつけるかが、日本版ライドシェアの成否を左右すると見ています。
ウォーレン・バフェット氏の投資姿勢:「誤りを直視せよ」という株主へのメッセージ
世界的投資家のウォーレン・バフェット氏は、毎年発行する「株主への手紙」で自身の経営観や投資哲学を公表しています。2024年の手紙では「誤り」に関する言及が多く、過去に見誤った投資や経営判断について率直に振り返っている点が興味深いです。
私も「企業経営や投資で失敗を犯さない人はいないが、一番の問題は誤りを先送りして自分もだまされること」というバフェット氏の考え方に強く共感します。どんなに不快でも、早期に誤りを認め修正することこそが、企業を長期的に成長させる要諦です。
バークシャー・ハザウェイは保険事業や鉄道・エネルギーなど幅広い分野で収益を確保し、アップルや日本の商社株にも積極的に投資してきました。ただ、近年は市場の乱高下もあって大量のキャッシュを抱える場面も見られます。私はこうした慎重な資金運用と、失敗を見極める冷静さこそが、バフェット氏の投資が長期にわたり成果を出している理由だと考えています。
憲法改正と日米安保の再検証:創憲への道筋を描く覚悟が問われる日本政治―
世論調査で「憲法を改正したほうが良い」という声が高まっていますが、中身に踏み込んだ具体的議論はまだ十分とは言えません。自民党は自衛隊の明記や緊急事態条項の創設などを挙げていますが、ドイツやイタリアなど諸外国のように何度も憲法を改正してきた国と比べれば、日本は一度も改正せずにここまできました。私は“改憲”というより、“創憲”と呼ぶくらいの大胆な見直しこそが必要だと思っています。
また、日米安保をめぐっては、トランプ前大統領が「日本は守ってもらうだけだ」と繰り返し発言しました。しかし、実際には日本は在日米軍の駐留経費負担や有事の共同作戦などを通じ、単なる片務的関係にとどまらない実態があります。
私が強調したいのは、憲法や安保のあり方を「現実に即した形」にアップデートし続けることです。周辺情勢や世界規模の安全保障環境が激変するなか、国際協調と国防のバランスをどこで取るかは日本の死活問題です。国民投票での合意形成には長い時間と丁寧な説明が必要ですが、根本的な制度改革を回避し続けるわけにはいきません。今こそ政治家が責任を持って将来像を提示すべきと強く感じています。
—この記事は2025年3月9日にBBTchで放映された大前研一ライブの内容を一部抜粋し編集しています。