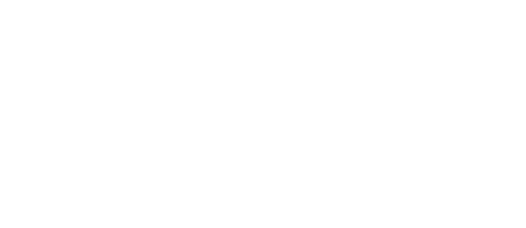1. 石破・トランプ首脳会談と投資戦略
日米同盟の再確認と日本製鉄のUSスチール買収構想
石破総理は7日、アメリカのトランプ大統領と初の首脳会談を行いました。会談では、日米同盟をインド太平洋地域の平和と安定の礎と再定義し、同盟関係を一層強化していく方針で一致したとされています。加えて、日本からアメリカへの投資額を一兆ドル規模まで拡大する意欲が示されましたが、具体的な投資対象の例として取り沙汰されたのが、日本製鉄によるUSスチール買収計画です。
しかし、公式発表では「買収」ではなく「投資」という表現が選ばれています。この背景には、アメリカ政府内の政治的配慮や、外資による経営権取得に対する国内世論への懸念があるとみられます。たとえば、ファンドを組み込むスキームや株式比率を制限する方式などが検討される可能性もあるようです。日本製鉄側としても、数兆円規模の投資を行う以上、経営主体としての影響力を行使しなければ株主への説明責任が問われるでしょう。一方で、アメリカ側としては地元雇用の確保や老朽設備への資金注入を歓迎する思惑があると考えられます。両国の利害が合致するのか、今後の経営方針・条件面の交渉が注目されます。
2. パナマ運河・ガザ地区・イラン核合意――揺れるトランプ外交
条約や歴史を軽視する姿勢への国際社会の反応
パナマ運河問題
トランプ政権はパナマ政府がアメリカ船舶の通行料を免除する合意を結んだと発表しましたが、パナマ側はこれを即座に否定しました。両者の主張が真っ向から食い違う原因の一つとして、パナマ運河の管理をめぐる米国とパナマの条約が挙げられます。アメリカ側が通行料を免除させることは、有事での例外規定はあるものの、永久中立を定めた条約に抵触する恐れが大きいのです。また、香港系企業であるハチソンを「中国資本」と誤解し、中国が運河を牛耳っているかのような認識が広がっている点も、事態をややこしくしている要因といえます。
ガザ地区を「アメリカで開発」構想
トランプ大統領はガザ地区を一時的に他国へ移住させたうえで、米国が「再開発」するという大胆な構想を語りました。しかし、二国家解決を目指す国連や中東諸国は、この提案を真剣に取り合っていません。背景には、歴史的経緯を踏まえたオスロ合意や国際協調の枠組みを無視する姿勢への反発があります。サウジアラビアなど有力国も「到底受け入れがたい」と表明しており、アメリカの伝統的同盟国すら困惑しているのが実情です。
イラン核合意再交渉の難航
トランプ政権は2018年にイラン核合意を一方的に離脱し、対イラン制裁を再開しましたが、今回は「新たな平和協定」を提案しています。しかし、イラン最高指導者ハメネイ氏はこれを拒否し、ヨーロッパ諸国も合意離脱の前例を理由に、アメリカへの信頼性を疑問視しています。国連が仲介した合意を破棄した当事者が、改めて交渉を求めても相手国が応じる保証はありません。こうした「決定を覆す」外交姿勢に対し、国際社会が慎重な姿勢を崩さないのは当然といえるでしょう。
3. アメリカ経済政策――貿易赤字・関税・仮想通貨の波紋
輸入構造の根深い問題と市場の混乱
止まらない貿易赤字
アメリカの財(モノ)の貿易赤字は年々拡大し、2024年には過去最大規模に達しました。輸出が伸び悩む一方で、低コストの輸入品が大量に流入していることが背景とされています。加えて、関税引き上げが予告されるたびに、事前に輸入を増やす「駆け込み需要」が生じるため、かえって赤字が拡大する構造になっています。一方、金融やITサービスといった分野では黒字を維持しているものの、製造業は回復の兆しを見せておらず、1980年代の日本との貿易摩擦以来の構造的な空洞化を解消できていません。
追加関税と外交取引
トランプ政権はカナダとメキシコへの25%関税を一時的に先送りする一方、中国からの輸入品には10%の追加関税を発動しました。メキシコ産の農産物やカナダからの原材料に課税すれば、アメリカ国内の物価が急上昇し、消費者に大きな負担が及ぶと試算されています。こうした現実的な懸念から、一部の項目のみを対象外とする可能性も取り沙汰されています。中国側も報復関税やWTOへの提訴で応じ、米中貿易摩擦が抜き差しならない状態に陥っています。
トランプコインの急落
トランプ大統領が公認したとされる仮想通貨「トランプ」は、一時2兆円超という目を疑うような時価総額を記録しましたが、その後90%以上も下落しています。政治的ブランドへの投機マネーが集まったものの、政権運営の迷走ぶりや世界経済の不透明感が強まったことで、投資家心理が急速に冷え込んだとみられます。短期間で巨大資金が動く仮想通貨市場の特性を象徴する事例となっています。
4. アメリカ政府内部の組織改革――FBI・CIA・CFPB・USAIDの再編
「効率化」の名の下で広がる混乱
司法長官の人事刷新に伴い、FBI内の「外国からの選挙介入」を担当する対策班が解散を命じられました。元々は2016年大統領選のロシア介入疑惑などを受けて強化された部門ですが、政権が「優先事項の見直し」を理由に削減する方針を示しています。さらにCIAでも早期退職の促進が通達され、消費者金融保護局(CFPB)の業務が一時停止されるなど、監督機能が大幅に縮小される動きが相次ぎました。これにはIT・金融業界の一部から歓迎の声もある一方で、国民の安全保障や消費者保護の観点からは弊害が大きいとする反対意見が根強いです。
また、1960年代から各国に人道支援を行ってきたUSAID(アメリカ国際開発局)についても、海外派遣職員を大量帰国させる決定が下されました。途上国支援や災害対応で重要な役割を担ってきた組織だけに、国際的な批判も高まっています。こうした大規模な組織再編は、連邦地裁が一部差し止め命令を出す事態にも発展しました。トランプ政権と司法の対立が続くなか、政府機能が混乱に陥るリスクが懸念されています。
5. 中国の巨大インフラ――チベットダムと高速鉄道の拡張
水資源外交と過剰投資の実態
チベット高原での大規模ダム
中国政府はチベット高原を流れるヤルンツァンポ川に、世界最大級のダムを建設する計画を打ち出しました。発電量が三峡ダムの3倍にも及ぶとされ、膨大な水力発電が見込まれます。しかし、下流域のインド側は領有権問題に加え、水資源が大幅に制限される懸念から強く反発しています。1962年の中印国境紛争以来、両国の国境地帯は一触即発の状態が続いており、水利権をめぐる争いは新たな火種になりかねません。ナイル川流域で起きたダム建設の国際紛争のように、対立が深刻化する可能性があります。
広がり続ける高速鉄道網
中国の高速鉄道は2025年末までに、総延長が5万キロメートルを超える見通しです。日本の新幹線(約3200キロメートル)の15倍という圧倒的スケールですが、需要が追いつかず稼働を停止する駅も各地に存在します。国内には依然として採算度外視の建設ラッシュを進める傾向があり、開発そのものが景気対策と結びついている面があるようです。しかし、莫大な建設費や維持費が将来的に財政の重荷となるリスクも指摘されています。インドネシアやアフリカなどの海外プロジェクトで同様の問題が表面化しつつあり、中国政府の巨大インフラ戦略には国際社会からの注視が続いています。
—この記事は2025年2月9日にBBTchで放映された大前研一ライブの内容を一部抜粋し編集しています。