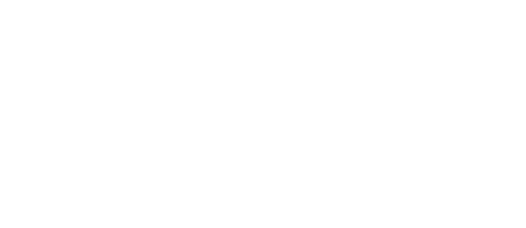防衛分野での日米AI連携:パランティア・テクノロジーズCEOが呼びかけ
防衛領域におけるAI開発の重要性が高まる中、アメリカのAIデータ解析大手であるパランティア・テクノロジーズ社のカープCEOは、日米が連携して技術開発を進めるべきだと強調しています。軍事や安全保障分野では、膨大な情報をいかに早く正確に分析し、有効な対応策を導き出すかが勝敗を左右する時代になりつつあります。
特に中国など権威主義国家の台頭を念頭に、AIによるリアルタイム解析が各国の軍事バランスに与える影響は無視できません。同社はアメリカ国防総省とも強い結びつきを持ち、ウクライナや中東における軍事情報の解析で豊富な実績を示してきました。日本企業や日本政府にとっては、AI開発のスピードやデータ管理のノウハウを共有する絶好の機会となりえますが、防衛活用に伴う情報漏えいや倫理面での問題も懸念されます。技術の高度化と運用拡大が急速に進む以上、情報セキュリティの強化や国際法との整合性を図るための議論が不可欠です。さらに日米が協力して開発したAI技術を第三国への輸出・移転をどこまで認めるかについても、国際協調の枠組みづくりが求められます。今後、政治・軍事の両面から調整を図りながら、新たな防衛戦略にAIを組み込む動きが一段と進むことが予想されます。
公示地価がバブル崩壊後最大の上昇率:外国マネーとインバウンド需要が地方にも波及
国土交通省が公表した公示地価によると、全国平均は前年比2.7%の上昇を記録し、バブル崩壊以降で最大の伸びとなりました。主な要因として、まず挙げられるのが円安と低金利による外国投資マネーの流入です。海外投資家にとっては安価な調達コストで日本の不動産を取得しやすくなっており、さらに観光客の回復も相まって、商業地を中心に需要が高まっています。特に都市部や人気リゾート地、スキーリゾート周辺などで顕著に地価が上昇し、インバウンド向けホテルや別荘開発が活発化しているようです。
しかし一方で、地方全域が一様に値上がりしているわけではなく、交通アクセスや観光資源が乏しい地域では地価がほとんど変動しない例も目立ちます。つまり、全国規模での二極化がさらに鮮明になり、高度な観光資源や大型開発の余地があるエリアが大きく値を上げるのに対し、人口減少が続く地域では低迷が続く構図です。今後は外国投資の動向に左右されやすい側面もあり、地元自治体としては持続可能な地域活性化や住宅政策をどう立案するかが、より重要になるでしょう。
大阪駅北側「グラングリーン」開業:商業・ホテル・カンファレンスが集結する新拠点
JR大阪駅の北側に広がる大規模再開発エリア「グラングリーン大阪」で、南館が開業し話題を集めています。商業施設は55店舗が出店し、ホテルやカンファレンス施設などが一体となった複合型の街づくりが進められました。初日には人気レストランに長蛇の列ができるなど、商業面の盛況ぶりは顕著で、大阪・関西万博の開催機運を追い風に、この地域がさらに活気づくことが期待されています。周辺には百貨店や大型ショッピングセンターが点在しており、梅田エリア全体が新たなランドマークを得たことで、国内外からの観光客やビジネス客が一層集まる可能性があります。大阪は以前から「水都」としての特徴や独特の食文化などで国内外の観光客を引き付けてきましたが、大規模な再開発が継続的に行われることで都市機能が強化され、国際会議や展示会、イベント誘致のポテンシャルも高まるでしょう。一方で、さらなる経済波及効果を生むには、地域住民や小規模事業者との連携、環境への配慮、そしてまちづくりの継続的なビジョンづくりが欠かせません。グラングリーン大阪は、大規模再開発が都市の魅力と経済活力をどのように高めていくかを示す試金石となりそうです。
アメリカ軍、イエメン反政府勢力を空爆:フーシ派の航路攻撃に対する大規模軍事行動
イエメンの反政府武装組織フーシ派が航海上の商船などを繰り返し攻撃しているとして、アメリカはフーシ派拠点への空爆を実施しました。アメリカ側は「決定的かつ強力な一撃を与えた」と主張し、海上の物流安全を守るための正当な措置であるとの立場です。しかし、フーシ派は即座に報復を宣言し、アメリカ軍艦を含む外国船舶への攻撃を辞さない姿勢を示しています。フーシ派はイランの支援を受けているとされ、イエメン内戦だけでなく、中東地域全体の覇権争いの一端を担う存在です。航路攻撃が激化すれば原油や物資の輸送にも影響が及び、世界のエネルギー市場に不安定要因をもたらしかねません。国際社会としては民間船舶の安全確保と人道支援を両立させるため、各国が協調して軍事的・外交的に働きかける必要があります。しかし、アメリカによる空爆がさらなる紛争拡大を引き起こす危険性もあり、長期的な地域安定には双方が和平交渉を進める体制づくりが欠かせません。今後、中東情勢を巡る主要国の協力やイランとの関係如何によって、イエメンの紛争構造も大きく左右されるでしょう。
ガザでの停戦崩壊、イスラエル軍が攻撃再開:人道合意の履行めぐりハマスと互いに非難
イスラエルとイスラム組織ハマスが一時的に停戦合意を結んでいたガザ地区で、再びイスラエル軍が攻撃を開始しました。イスラエル側は「ハマスが人質の解放を拒否し続けた」として武力行使を正当化していますが、ハマス側は「イスラエルが停戦協定を守らず、人道支援物資の搬入も制限した」と反論しており、両者の主張は平行線をたどっています。当初、合意には捕虜交換や市民の避難経路の確保などが盛り込まれていたものの、実際には実行が滞り、街のインフラは激しく破壊されて住民生活は一層困窮しています。ガザ地区は人口密度が高いため、軍事行動は大規模な人的被害をもたらす危険があり、国際的な非難も強まるばかりです。停戦の再実現に向けては、外交努力が急務である一方、イスラエルとハマスの相互不信を取り除くのは容易ではありません。各国による仲介や国連の調停が試みられているものの、周辺諸国の利害や歴史的な対立が絡んでおり、解決への道筋は見通せない状況です。人道危機を食い止めるため、少なくとも負傷者救護や市民の退避に関しては迅速かつ包括的な合意形成が望まれます。
ロシア、ウクライナのインフラ攻撃を一時停止:トランプ大統領との電話協議で30日間の合意も全面停戦は見えず
アメリカのトランプ大統領は、ロシアのプーチン大統領との長時間の電話協議を経て、ロシア軍がウクライナの主要エネルギー施設への攻撃を30日間停止することに合意したと発表しました。しかしロシア側は、ウクライナがEUやNATOへの接近をやめない限り、根本的な解決には至らないとの強硬姿勢を崩しておらず、全面的な停戦を受け入れる兆しはありません。現地でも実際に、エネルギーインフラ以外の施設や民間地域への攻撃が続く可能性が指摘され、ウクライナのゼレンスキー大統領は合意内容の曖昧さに懸念を表明しています。そもそも、ウクライナ側が期待する領土問題の解決や安全保障の保証が不十分なままでは、長期的な安定につながりにくい状況です。一時的な合意がどれほど現場に効力を持つか疑問視される中、アメリカなど欧米諸国も対ロシア制裁や軍事的支援の度合いを調整しながら、外交交渉で糸口を探っています。とはいえ当事者間の主張の隔たりは大きく、複雑な地政学的利害も絡むため、停戦実現に向けた道のりは依然として険しいといえます。
トランプ政権:米国メディアの独立、教育省解体構想、次世代戦闘機F47計画の行方
トランプ政権期には、メディアや教育、軍事分野で一連の大きな動きが見られました。まず「Voice of America」の大量解雇問題では、政府系メディアとして独裁国家への情報発信を使命としてきた組織が、政権の方針によって編集や報道の独立性を脅かされる事態が浮上しました。SNSにおける「反トランプ的」発言を理由に、1300人以上のスタッフが休職命令を受けたことで、報道機関としての信頼性や自由主義の根幹を揺るがすとの批判が高まったのです。次に教育省の解体構想では、連邦レベルから州や地方自治体に教育の権限を移譲し、中央集権的な制度を改める狙いが示されました。アメリカの学校運営は本来、学区単位で独立性を持つため直接の影響は限定的ともいわれますが、連邦予算の配分などが変わる可能性があり、混乱も懸念されます。そして米空軍の次世代戦闘機「F47」構想では、トランプ大統領が自ら命名し、わずか数年で実用化すると豪語したものの、専門家からは10年ほどの開発期間が必要と指摘されています。ステルス性能や無人機連携など革新的技術を盛り込む一方、大統領の政治的意向が予算や計画全体に影響を及ぼすことを不安視する声もあり、実現のスケジュールは依然不透明です。
香港CKハチソン、パナマ運河の権益売却へ:中国政府は「国益を損なう」と猛反発
香港を拠点とするCKハチソンホールディングスが、パナマ運河周辺の港湾運営権をアメリカのブラックロックなどに売却すると発表し、中国政府から激しい批判を受けています。中国国務院香港マカオ事務弁公室は「国益を裏切る行為だ」と断じ、同社株価も一時急落しました。もともとCKハチソンは英国系資本に端を発するグローバル企業であり、中国本土とは一線を画した経営を行ってきた背景があります。世界各地の港湾運営に実績を持ち、経済合理性に基づく判断として売却を決断したとみられますが、中国当局は政治的思惑が絡む海外戦略資産の喪失を懸念しているようです。近年は「一帯一路」構想をはじめ、中国が港湾インフラを地政学的な武器として重視する事例も多く、香港企業による海外資産の売却が中国政府の「影響力縮小」と受け止められる可能性があります。CKハチソンとしては、ビジネス優先の方針でグローバル展開を続ける姿勢を示す一方、今後は中国本土との政治的摩擦が増す恐れもあり、経営リスクがさらに高まることが想定されます。
インド高速鉄道にE10系採用検討:JR東日本の次世代新幹線が海外進出なるか
インド政府が西部で進める高速鉄道プロジェクトで、JR東日本の次世代車両E10系を採用する案が浮上しています。モディ首相の出身地アーメダバードから商都ムンバイを結ぶ路線は、インド経済を牽引する重要交通インフラとなる見込みで、日本の新幹線技術が採用されれば国際的にも大きな注目を集めるでしょう。日本の鉄道システムは安全性や定時運行、快適性で高い評価を得ていますが、インド特有の人口密集や用地取得の難しさ、資金調達などの問題が山積しています。また、州政府や複数の民間資本が絡む複雑な調整も必要で、工期や費用が想定以上に膨らむリスクもあります。しかしE10系のような最新車両を投入できれば、車内環境の向上やスピードアップだけでなく、省エネ性能のアピールも可能です。インドでは近年、インフラ整備に積極投資を行い、海外技術を積極的に導入する姿勢を打ち出しているため、実現の可能性は十分にあります。もし採用されれば、日本の新幹線方式がインドの経済発展と交通改革にどう寄与するか、また他国への展開に弾みがつくかが大きな焦点となるでしょう。
タイへの外国直接投資が増加:米関税政策の回避で生産拠点シフト
タイ投資委員会の統計によると、2024年における外国からの直接投資額は前年比で25%増加し、総額約3.7兆円に達したと報告されました。背景にはアメリカのトランプ政権が中国製品に対して強化した関税政策があり、多国籍企業が生産拠点を中国から東南アジアに移す動きが加速しているとみられます。タイはASEAN諸国の中でも政治が比較的安定しているうえ、産業インフラや物流網も整備されており、自動車や電子部品など多様な製造業が集積しやすい環境が整っています。従来は日本企業が自動車産業を中心に積極進出してきましたが、最近は中国系の電子企業も相次いで投資し、現地生産を拡大するケースが増えました。一方で、人件費の上昇や大都市部での地価高騰、さらに労働力の確保など課題も少なくありません。東南アジア全体が巨大市場として注目される中、タイ政府は税制優遇やインフラ開発を前面に打ち出し、海外企業誘致を強化している状況です。今後も世界経済の流れによって投資先が変化する可能性はありますが、タイは引き続き重要な製造・輸出拠点として地位を高めていくと考えられます。
—この記事は2025年3月23日にBBTchで放映された大前研一ライブの内容を一部抜粋し編集しています。