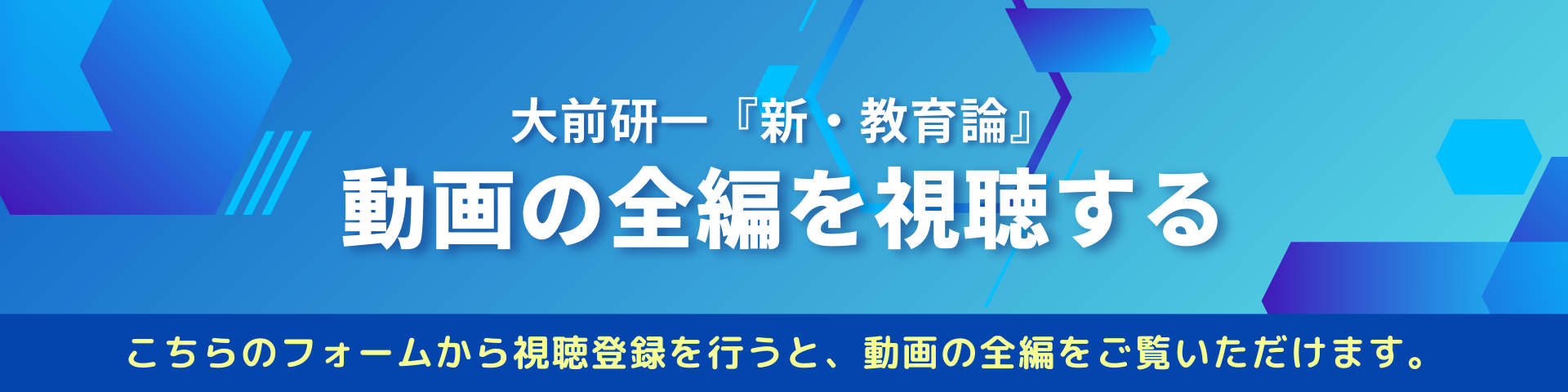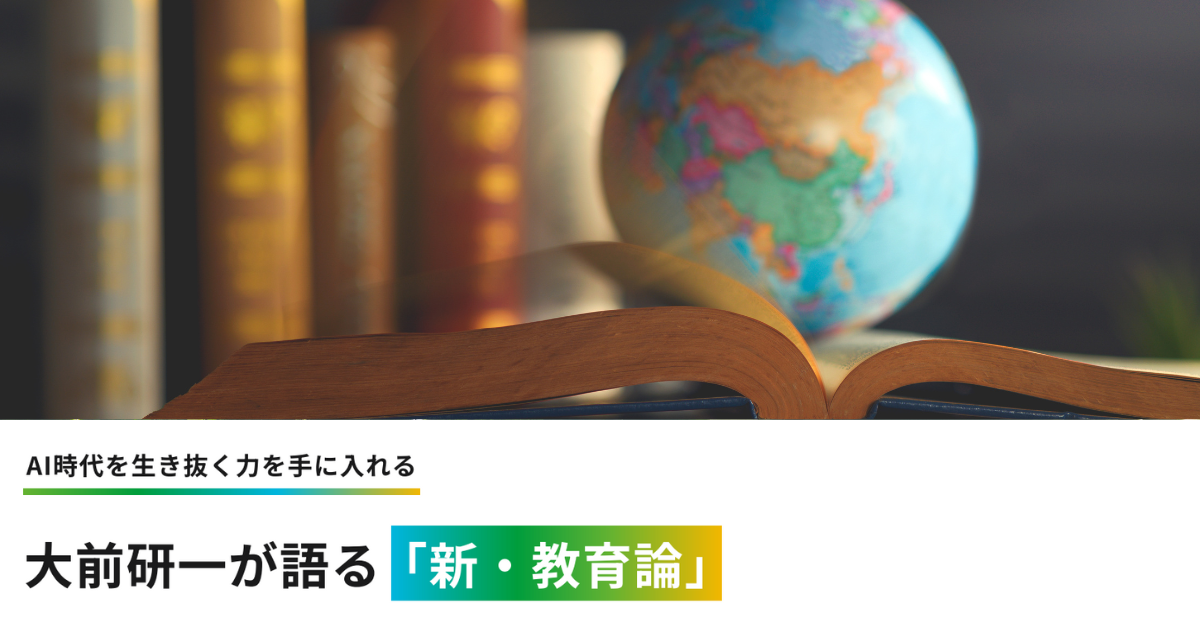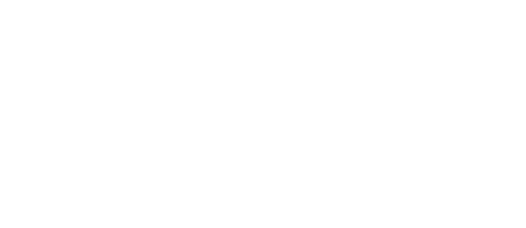答えなき時代の教育のあり方とは vol.2
実践的な学びを阻む国内の教育制度
20世紀型教育の限界
日本の教育制度は20世紀型の教育を基盤としており、知識のインプット中心のカリキュラムがなお主流となっています。工業化社会においては、座学による詰め込み教育で標準的な学力の底上げに成功しましたが、21世紀に必要とされるのはアウトプット重視の学びです。すなわち、創造性や実践力、そして急激な変化に対応する柔軟性が求められます。デンマークでは1994年に「教師が教える」から「生徒がディスカッションを通じて学ぶ」方式へ移行しましたが、日本では指導要領の改訂が10年単位であるため、デジタル化やグローバル化などの動きをタイムリーに取り込むことが難しくなっています。
改革を打ち出しているように見えても、実際の現場では講義形式の授業が依然として主流です。結果として、生徒が主体的に学び、問題解決能力やコミュニケーション能力を身につける機会が限られており、学習意欲が十分に引き出されていない実態があります。
文系・理系の選択制度と推薦入学制度
高校での文系・理系の選択制度も実践的な学びを阻害しています。文系は受験科目が少なく、比較的容易と見なされるため、多くの生徒が安易に文系を選び、結果的に理系分野を志す学生が不足しているのです。海外では理系教育をすべての生徒が学ぶことを前提とし、文系科目を教養として位置づける国が多く、早期に文系・理系を分断する日本の制度は時代に合わなくなってきています。
推薦入学制度についても問題は深刻です。推薦が決まった時点で学習意欲が低下し、大学入学後の基礎学力が不足するケースが増えています。特に理系学部では、高校までに身につけるべき微分積分や物理の基礎知識が欠如したまま入学し、補習を要する学生が目立つようになりました。これは高等教育全体の水準を下げるだけでなく、研究や高度な専門教育における実践力をそぐ原因にもなっています。
大学教育の変革と学びへの動機づけ
大学教育そのものについても、大きな見直しが求められています。従来は「卒業証書を取得すること」が目的化しがちでしたが、コロナ禍以降、「必要なスキルを短期間で身につけたい」というニーズが高まりました。プログラミングやAIマーケティングなどを集中的に学ぶ短期プログラムが注目され、四年制大学には専門的かつ高度な研究や教育を担う役割がいっそう期待されています。
また、大学無償化が進むなかで、学生が学びを自己投資と捉える意識が希薄になっているのも課題です。多くの国では、卒業後の収入に応じて学費を返済する仕組みを導入し、学生のモチベーションと責任感を高めようとしています。こうした制度を日本でも導入することで、学びの主体性を強化し、大学教育の質を向上させることが期待されています。
—この記事は、11月に開催された向研会での講演『新・教育論』の内容を一部抜粋し、編集したものです。講演内容を全編視聴されたい方は、以下のリンクよりご視聴いただけます。